個人的な体験談になりますが、今の勤務先に入社した数年前、上司とトラブルを起こしてしまい、兼任で担当していたデザインの仕事から外されました。
朝夕の唱題祈念で
「デザインの仕事を担当できますように」
と祈っていましたが、見通しは立たず…。
感じていたのは「祈り」の最中だけ、将来への不思議な確信が湧いてくる、という実感!
こうなると超自然的な存在である、十界文字曼荼羅本尊に身をまかせるしかありません。参考書を買ってAdobeツールの使い方を勉強するなどの努力はしませんでしたし、する気にはなれませんでした。
そんな状況でしたが昨年、デザイン(紙媒体の広告)の仕事に思わぬ形で参画。さらに発注元から高評価を受け、わたしのデザインが採用されることに。会社始まって以来の、外部から受注したデザインの仕事でしたので内部での評価も一変しました。
そのことで、会社が運営するポータルのWebデザインの一端を担うことに。勉強を怠ってきたので悪戦苦闘していますが、やっぱり夢中になれる仕事はいいものです。
わたしが日蓮正宗の寺院に来る前に所属していた「顕正会」では 『法華経に勝る兵法なし』 とはいいますが、一発ものの体験談で終わってしまうことが多い。布教勧誘の席でも何年も前の〝よいことがあった〟体験談を話すことも。
そもそもその人自身には体験談らしいものがなく、同じ組織内の体験とか、機関紙に掲載されている体験とかを喜々得々と話すことも多いのです。
日蓮正宗の寺院に所属し、お題目を実践していて思うのは
なによりも自分の身で、
そして何回も大小の功徳と罰の体験を積み重ねないと本来は『法華経に勝る兵法なし』とは言えないということですね。
まさに「積功累徳(しゃっくるいとく)」とはこのことのためにあるような言葉です。
さらに、痛感しているのは、祈りは確かに叶う。
どんな祈りでも叶うけれども、それが将来的な道を切り拓くかどうかは、また日々の勉強・努力と、何よりも「お題目」にかかってくるということです。
仕事も、勉強も、お題目も、いい加減な気持ちで取り組んでいてはいけません。
御書にある通り、「をんみやづかいを法華経とおぼしめせ」、すなわち日々の仕事が法華経の実践でもあるのです。
一発ものの体験で終わらせないためには、日々の仕事に・お題目に、歓喜と渇仰恋慕で取り組むことです。「顕正会」では日々の布教勧誘の活動で手いっぱいで、お題目をしっかり唱えることすらままならない。
わたしが「顕正会」を脱会し、日蓮正宗の信仰に入って良かったと思うのは
『法華経に勝る兵法なし』の意味が、違うこと。
「顕正会」では「布教勧誘のノルマを達成していくことで生活も潤う」という意味だったのに対して、
日蓮正宗の信仰では「(御本尊に対して)お題目をしっかり唱えればあらゆる苦悩・苦難を乗り越えていける」という意味であるのです。
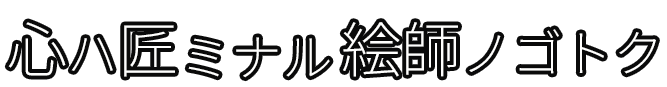
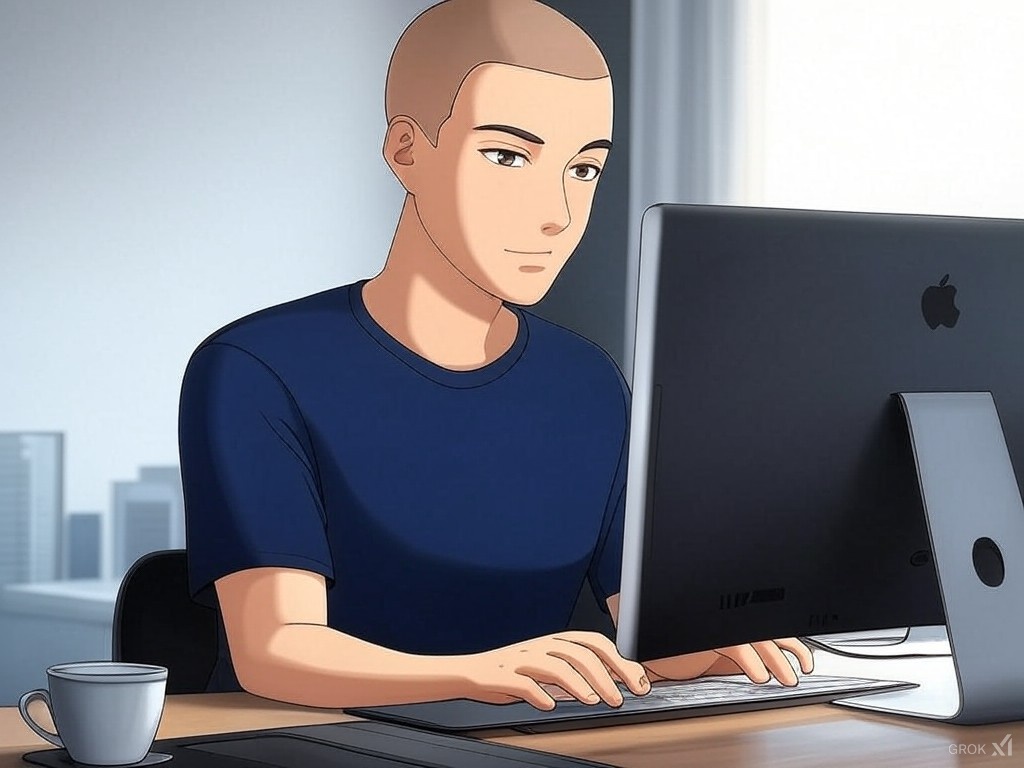


コメント